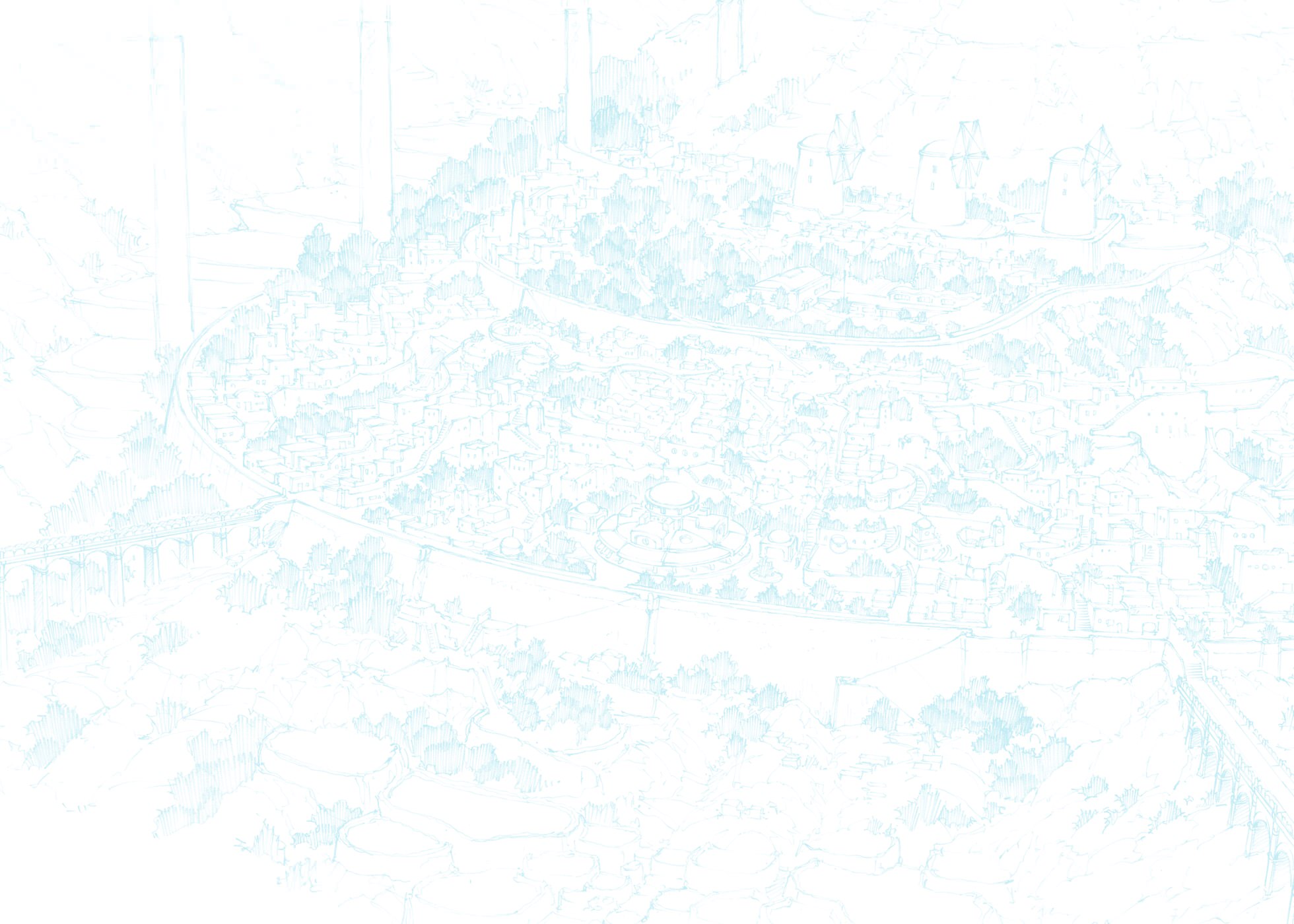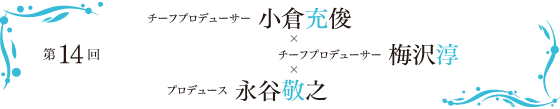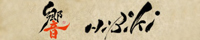——まずは企画立ち上げについてお聞かせください。
永谷
『凪のあすから』は、新しいプロデューサーに作品をまかせてP.A.WORKSの新たなカラーを出したい、というところから始まりました。今までのP.A.WORKS作品は、堀川(憲司/P.A.WORKS代表取締役)さんが中心となって作品を作ってきましたが、堀川さんの場合、物語よりもまずテーマがある。「こういうテーマを描きたいから、こういうお話を作りたい」ということが基本にありました。それはP.A.WORKSらしさであり、今後も続いていくものです。ただ違う切り口、別のラインでやってみたらどんな作品が出来るんだろうと。それは堀川さんと2枚看板にしたいということではなく、『花咲くいろは』(2011年)でスタジオ設立10周年を迎えスタッフも成長してきた中で、別のアプローチをしてみたかった。そこでP.A.WORKS初期から堀川さんと一緒に作品を作ってきた辻(充仁)君に声を掛けたんです。
——梅澤さん、小倉さんはどのタイミングで参加されたのですか?
梅澤
アニメーションプロデューサーが辻さんに決まってから、そんなに時間は経っていないと思います。作品の携わり方はその時々で違いますが、今回は「電撃大王さんとP.A.WORKSさんでひとつの物語を作りましょう」と永谷さんからご連絡いただきました。
小倉
僕たちはその後くらいですね。脚本作業に入る前でしたが、“ファンタジー”“恋愛”というキーワードはあったと思います。P.A.WORKSさんで久々に恋愛をテーマにした作品を準備しているとお聞きして、参加させていただけるならぜひ! という感じでした。
永谷
梅澤さんが言われたように作品によってお願いの仕方は様々で、場合によっては「こういう作品が進んでいるのですが、参加していただけませんか?」とお声掛けすることもあります。ただ今回は0から1にする瞬間、作品が生み出されて動き出す瞬間を皆さんで共有したかったんです。簡単に言えば仲間を集めてパーティを作り、そこから動き出したという感じでしょうか(笑)。
——なるほど(笑)。梅澤さんや小倉さんは『凪のあすから』に参加される前、P.A.WORKSさんにはどんな印象を持たれていましたか?
梅澤
P.A.WORKSさんの手掛けるアニメは地に足のついた作品が多く、日常芝居をしっかり描かれるスタジオという印象がありました。数多くあるアニメスタジオの中でもどこか一線を画していて、いつかは組んでみたいと思っていたんです。実は別の編集部が『Angel Beats!』という作品を一緒にやらせてもらっているんですが、その時は羨ましいなぁと思って見ていました(笑)。そういう意味では今回お話をいただいた時、断る理由はなかったですね。
小倉
僕はとても丁寧な映像を作られるアニメスタジオという印象でした。それに加えて、これだけいいフィルムをどうやって作っているんだろう? という興味もありましたね。
梅澤
僕もそこは気になっていました。これだけのフィルムを作られるのには、いろいろな要素があると思うのですが、今回組ませていただいて感じたのは、“アットホーム”ということ。スタジオがとても温かいんですよね。こういう雰囲気だからこそ、あそこまでのフィルムが出来るのかなって思いました。
永谷
そこがP.A.WORKSというスタジオのいいところでもあり、辻君が初のアニメーションプロデューサーとして難しいと感じている部分でもあると思うんです。プロデューサー、特にアニメスタジオ側のプロデューサーは、制作現場と我々の間に立っていろいろなジャッジをしなくてはいけないし、時には現場に厳しい要求を突き付けることもある。でも今はどうしても現場に甘いジャッジをしてしまうことも多いかなって(苦笑)。そこは今後いろいろと経験を積んで、バランスを身に着けてもらいたいですね。
——みなさんがプロデューサーとして制作に携われて、一番悩まれた部分はどこでしょうか?
梅澤
「どこまでリアルにして、どこまでファンタジーにするか」というところです。『凪のあすから』はおとぎ話をベースにする部分があったので、ある程度ファンタジーな世界でいいと思っていました。でもファンタジーだけだとアニメの演出として成立しない部分が多々あり、紆余曲折しましたね。特に篠原監督や辻さんは相当悩まれていて、企画立ち上げから“エナ”が出てくるまで、時間がかかりました。
小倉
明確なビジュアルがなく、テキストベースで話している企画立ち上げ当初は、皆さんのイメージが若干違っていた気がしました。同じ題材でも篠原監督、岡田さん、辻さん、梅澤さんや永谷さんの思い描いていることが少しずつズレていてる。それはどれも正解であり不正解でもあるです。僕らは少しだけ後発でしたから皆さんの考えていることを読み解くのに苦労しました。ただ梅澤さんが言われた“エナ”、そしてビジュアルが徐々に出てきてからは、一気に今の『凪のあすから』の世界に近づいていきましたね。
——ファンタジーを題材としたオリジナル作品ですから、明確な正解がないというのも難しいですよね。
小倉
そうなんですよね。これが現実の物語だったらそんなに迷わないですし、宇宙船やロボットが出てきたとしても現実の延長線上で考えられるので、そこまで苦労はしなかったと思います。今回は海の中の町があって、そこには地上と変わらない生活をしている人たちがいると。そして海の民は地上と対立している。見たことがないものばかりでしたから難しかった。ただその反面、やりがいや新鮮さを感じたのも事実です。
——そう言えば主人公たちの年齢を14歳(中学二年生)に推されたのは梅澤さんなんですよね?
梅澤
そうですね。『凪のあすから』ではプロデューサーとして、出版関係を中心にプロデュースするのが主な仕事ですが、その一方で『凪のあすから』の“萌えチェッカー”でもあります。「これは萌えるか? 萌えないのか!?」という判断をする。趣味の延長線上なんですけど(笑)。
小倉
シナリオ打ち合わせの時「どうですか梅澤さん?」っていう確認が入るという(笑)。
梅澤
そこは自分の感覚的なものなのですが、得意なところだと思っています。光たちを14歳にしたのも個人的に14歳がどストライクだから(笑)。具体的に言えば、14歳という時期は子供から大人になる年齢であり、自意識なども芽生えてきてドラマとしてもいろいろと作りやすい。そう思って14歳はどうですか? って提案したんです。そんなに力説したつもりはないんですけどね。
永谷
いや、力説してましたよ(笑)。
永谷
『凪のあすから』は、新しいプロデューサーに作品をまかせてP.A.WORKSの新たなカラーを出したい、というところから始まりました。今までのP.A.WORKS作品は、堀川(憲司/P.A.WORKS代表取締役)さんが中心となって作品を作ってきましたが、堀川さんの場合、物語よりもまずテーマがある。「こういうテーマを描きたいから、こういうお話を作りたい」ということが基本にありました。それはP.A.WORKSらしさであり、今後も続いていくものです。ただ違う切り口、別のラインでやってみたらどんな作品が出来るんだろうと。それは堀川さんと2枚看板にしたいということではなく、『花咲くいろは』(2011年)でスタジオ設立10周年を迎えスタッフも成長してきた中で、別のアプローチをしてみたかった。そこでP.A.WORKS初期から堀川さんと一緒に作品を作ってきた辻(充仁)君に声を掛けたんです。
——梅澤さん、小倉さんはどのタイミングで参加されたのですか?
梅澤
アニメーションプロデューサーが辻さんに決まってから、そんなに時間は経っていないと思います。作品の携わり方はその時々で違いますが、今回は「電撃大王さんとP.A.WORKSさんでひとつの物語を作りましょう」と永谷さんからご連絡いただきました。
小倉
僕たちはその後くらいですね。脚本作業に入る前でしたが、“ファンタジー”“恋愛”というキーワードはあったと思います。P.A.WORKSさんで久々に恋愛をテーマにした作品を準備しているとお聞きして、参加させていただけるならぜひ! という感じでした。
永谷
梅澤さんが言われたように作品によってお願いの仕方は様々で、場合によっては「こういう作品が進んでいるのですが、参加していただけませんか?」とお声掛けすることもあります。ただ今回は0から1にする瞬間、作品が生み出されて動き出す瞬間を皆さんで共有したかったんです。簡単に言えば仲間を集めてパーティを作り、そこから動き出したという感じでしょうか(笑)。
——なるほど(笑)。梅澤さんや小倉さんは『凪のあすから』に参加される前、P.A.WORKSさんにはどんな印象を持たれていましたか?
梅澤
P.A.WORKSさんの手掛けるアニメは地に足のついた作品が多く、日常芝居をしっかり描かれるスタジオという印象がありました。数多くあるアニメスタジオの中でもどこか一線を画していて、いつかは組んでみたいと思っていたんです。実は別の編集部が『Angel Beats!』という作品を一緒にやらせてもらっているんですが、その時は羨ましいなぁと思って見ていました(笑)。そういう意味では今回お話をいただいた時、断る理由はなかったですね。
小倉
僕はとても丁寧な映像を作られるアニメスタジオという印象でした。それに加えて、これだけいいフィルムをどうやって作っているんだろう? という興味もありましたね。
梅澤
僕もそこは気になっていました。これだけのフィルムを作られるのには、いろいろな要素があると思うのですが、今回組ませていただいて感じたのは、“アットホーム”ということ。スタジオがとても温かいんですよね。こういう雰囲気だからこそ、あそこまでのフィルムが出来るのかなって思いました。
永谷
そこがP.A.WORKSというスタジオのいいところでもあり、辻君が初のアニメーションプロデューサーとして難しいと感じている部分でもあると思うんです。プロデューサー、特にアニメスタジオ側のプロデューサーは、制作現場と我々の間に立っていろいろなジャッジをしなくてはいけないし、時には現場に厳しい要求を突き付けることもある。でも今はどうしても現場に甘いジャッジをしてしまうことも多いかなって(苦笑)。そこは今後いろいろと経験を積んで、バランスを身に着けてもらいたいですね。
——みなさんがプロデューサーとして制作に携われて、一番悩まれた部分はどこでしょうか?
梅澤
「どこまでリアルにして、どこまでファンタジーにするか」というところです。『凪のあすから』はおとぎ話をベースにする部分があったので、ある程度ファンタジーな世界でいいと思っていました。でもファンタジーだけだとアニメの演出として成立しない部分が多々あり、紆余曲折しましたね。特に篠原監督や辻さんは相当悩まれていて、企画立ち上げから“エナ”が出てくるまで、時間がかかりました。
小倉
明確なビジュアルがなく、テキストベースで話している企画立ち上げ当初は、皆さんのイメージが若干違っていた気がしました。同じ題材でも篠原監督、岡田さん、辻さん、梅澤さんや永谷さんの思い描いていることが少しずつズレていてる。それはどれも正解であり不正解でもあるです。僕らは少しだけ後発でしたから皆さんの考えていることを読み解くのに苦労しました。ただ梅澤さんが言われた“エナ”、そしてビジュアルが徐々に出てきてからは、一気に今の『凪のあすから』の世界に近づいていきましたね。
——ファンタジーを題材としたオリジナル作品ですから、明確な正解がないというのも難しいですよね。
小倉
そうなんですよね。これが現実の物語だったらそんなに迷わないですし、宇宙船やロボットが出てきたとしても現実の延長線上で考えられるので、そこまで苦労はしなかったと思います。今回は海の中の町があって、そこには地上と変わらない生活をしている人たちがいると。そして海の民は地上と対立している。見たことがないものばかりでしたから難しかった。ただその反面、やりがいや新鮮さを感じたのも事実です。
——そう言えば主人公たちの年齢を14歳(中学二年生)に推されたのは梅澤さんなんですよね?
梅澤
そうですね。『凪のあすから』ではプロデューサーとして、出版関係を中心にプロデュースするのが主な仕事ですが、その一方で『凪のあすから』の“萌えチェッカー”でもあります。「これは萌えるか? 萌えないのか!?」という判断をする。趣味の延長線上なんですけど(笑)。
小倉
シナリオ打ち合わせの時「どうですか梅澤さん?」っていう確認が入るという(笑)。
梅澤
そこは自分の感覚的なものなのですが、得意なところだと思っています。光たちを14歳にしたのも個人的に14歳がどストライクだから(笑)。具体的に言えば、14歳という時期は子供から大人になる年齢であり、自意識なども芽生えてきてドラマとしてもいろいろと作りやすい。そう思って14歳はどうですか? って提案したんです。そんなに力説したつもりはないんですけどね。
永谷
いや、力説してましたよ(笑)。